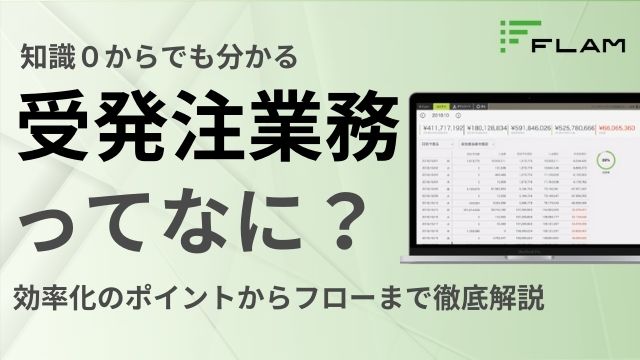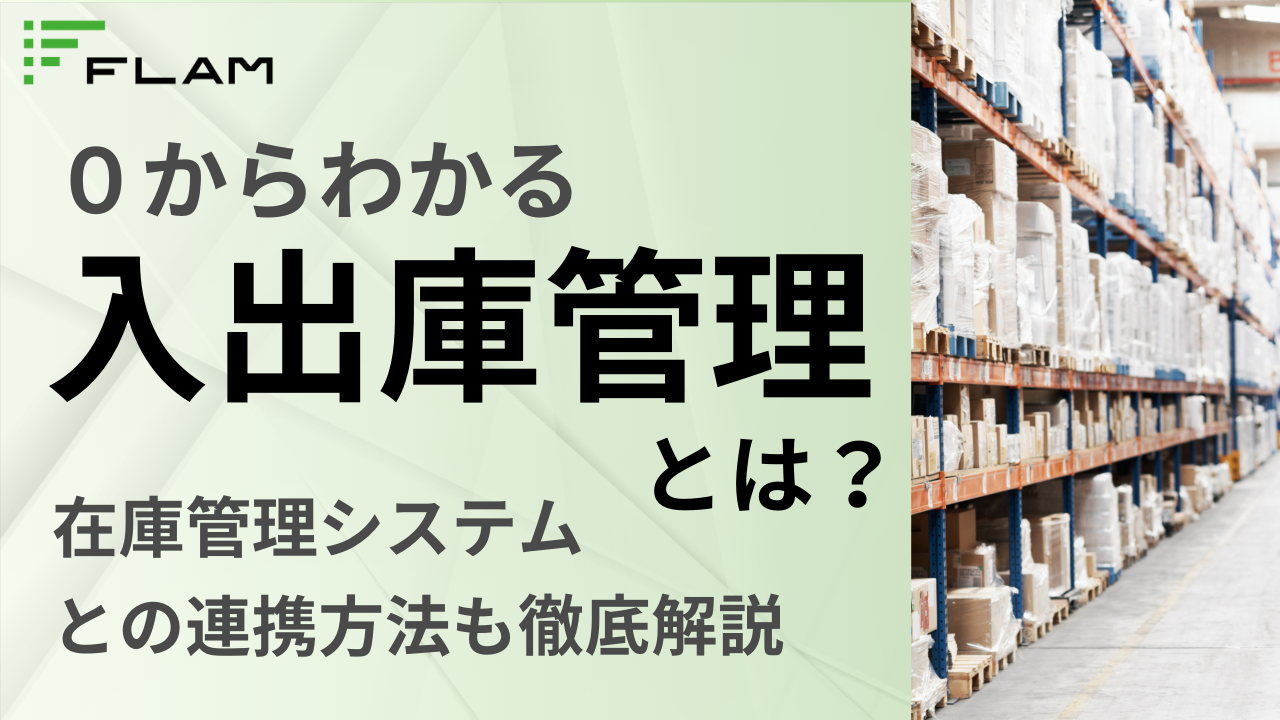生産管理システムとは?機能や導入によるメリット、選び方などを解説します

製造業において、生産性向上や業務効率化は常に重要な課題です。これらの課題を解決する有効な手段の一つとして、生産管理システムの導入が挙げられます。本記事では、生産管理システムの基本的な知識から、導入によるメリット、自社に合ったシステムの選び方までを分かりやすく解説します。
生産管理システムとは
生産管理システムは、製造業の根幹を支えるソリューションであり、製品の生産に関わるあらゆる業務を一元的に管理する基本的な仕組みを備えています。紙やExcelによる管理からシステム化することで、業務の自動化や効率化、生産性の向上を実現します。具体的には、生産計画、予算管理、資材管理、工程管理、在庫管理、品質管理など、製造業における幅広い業務を効率的に管理することが可能です。
生産管理とは
生産管理とは、製造業において、顧客の需要を満たすために必要な製品を、適切な品質、コスト、納期で生産するための管理活動全般を指します。具体的には、「何を」「いくつ」「いつまでに」作るかを計画し、その計画に基づいて製造プロセスを円滑に進めることを含みます。工場における資材の調達から製造、そして顧客への納品までの一連の流れを効率的に管理し、品質の維持やコストの削減、納期遵守を目指します。また、製品が完成してから顧客に届くまでの過程や、使用されている部品の調達元などを追跡可能にするトレーサビリティの確保も重要な目的の一つです。
生産管理システムが必要とされる背景
近年の製造業は、市場ニーズの多様化やグローバル競争の激化により、変化への迅速な対応が求められています。このような状況下で、従来の紙や表計算ソフトによる管理では、業務が煩雑化し、人的ミスが発生しやすい、情報共有が遅れるといった問題点が生じやすくなります。また、特定の熟練作業者に業務が集中する属人化も課題となります。さらに、サプライチェーンの複雑化やリードタイム短縮の要求も高まっており、これらの課題に対応するためには、生産に関わる情報を一元管理し、「見える化」できるシステムの導入が必要とされています。
販売管理システムとの違い
販売管理システムが主に「モノをどのように販売するか」に焦点を当て、見積もり、受注、出荷、請求、売上といった販売活動に関する情報を管理するのに対し、生産管理システムは「モノをどのように作るか」に焦点を当て、生産計画、資材調達、製造工程、在庫といった生産活動に関する情報を管理します。両システムは異なる役割を持ちますが、連携することで、受注情報に基づいた正確な生産計画の立案や、生産状況を考慮した納期回答が可能となり、より効率的な企業活動を実現できます。
ERPやMESとの違い
生産管理システム、ERP、MESはそれぞれ製造業で利用されるシステムですが、管理する範囲や目的に違いがあります。ERP(EnterpriseResourcePlanning)は「統合基幹業務システム」と訳され、会計、人事、販売、購買、生産など、企業全体の基幹業務を統合的に管理し、経営資源の最適化を目指すシステムです。一方、MES(ManufacturingExecutionSystem)は「製造実行システム」の略で、製造現場のリアルタイムな状況管理に特化しており、製造指示、工程管理、品質管理、実績収集などを担当します。生産管理システムは、製造業における生産活動全般を管理するシステムであり、ERPの一機能として含まれる場合や、MESと連携して使用される場合があります。ERPは企業全体、MESは製造現場、生産管理システムはその中間として、生産に関わる広範な業務を管理するという違いでわかりやすく整理できます。
生産管理システムの主な機能
生産管理システムには、製造業の複雑な業務プロセスを効率化し、全体を「見える化」するための様々な機能が搭載されています。これらの基本的な機能が連携することで、生産活動に関する情報を一元管理し、最適な意思決定を支援します。主な機能構成としては、計画系、管理系、分析系などが挙げられますが、ここでは中心となる機能を一覧でご紹介します。
生産計画機能
生産計画機能は、生産管理システムの根幹をなす機能の一つです。受注情報や需要予測、現在の在庫状況などを基に、「何を、いつまでに、いくつ生産するか」という詳細な生産計画を立案します。この機能により、過剰生産や生産不足を防ぎ、適切な量の製品を適切なタイミングで生産することが可能となります。設備や人員の負荷状況を考慮した計画立案や、ガントチャート形式での視覚的なスケジュール管理ができるシステムもあります。また、製品を構成する部品や材料の情報を管理するマスターデータ(部品表マスタなど)と連携し、必要な資材量を算出する機能も含まれます。
受注・販売管理機能
受注・販売管理機能は、顧客からの注文に関する情報を一元管理します。具体的には、注文内容の登録、納期確認、製品の出荷指示、売上計上などを行います。生産管理システムと連携することで、受注状況をリアルタイムに把握し、生産計画に反映させることが可能になります。これにより、納期遅延や誤出荷を防ぎ、顧客満足度の向上に貢献します。また、顧客ごとの販売実績を管理し、今後の需要予測や販売戦略立案に役立てることもできます。
資材管理・購買管理機能
資材管理・購買管理機能は、製品製造に必要な部品や原材料、消耗品などの資材に関する情報を管理します。具体的には、必要な資材量の算出(所要量計算)、仕入先への発注、納期管理、入荷検品などを行います。生産計画に基づき必要な資材を過不足なく調達するための重要な機能であり、適切な在庫量を維持し、生産の遅延を防ぐことに貢献します。また、仕入価格の管理や過去の取引履歴の確認により、コスト削減や最適な仕入先の選定にも役立ちます。
在庫管理機能
在庫管理機能は、工場や倉庫にある製品、部品、原材料などの在庫状況をリアルタイムに管理します。現在の在庫数の把握だけでなく、入庫・出庫履歴の追跡、適切な在庫レベルの維持、滞留在庫の特定などを行います。ロット管理機能を持つシステムでは、特定の製造ロットに紐づく製品や部品の追跡が可能となり、品質問題発生時の原因究明や対象製品の特定に役立ちます。適切な在庫管理は、過剰在庫によるコスト増や、在庫不足による生産停止や納期遅延を防ぐために不可欠な機能です。
製造・工程管理機能
製造・工程管理機能は、実際の製造現場における作業の進捗状況を管理します。生産計画に基づき、各工程への作業指示、作業実績の収集、進捗状況のリアルタイムな把握を行います。工程管理機能により、製造ライン全体の「見える化」が進み、ボトルネックとなっている工程や遅延が発生している箇所を早期に発見できます。また、組立作業など、複数の工程を経て製品が完成する場合の各工程の進捗も詳細に管理し、計画からのズレを把握することで、迅速な対策を講じることが可能となります。
原価管理機能
原価管理機能は、製品の製造にかかる費用を正確に計算し、管理するための機能です。材料費、労務費、経費などを製品別や工程別に集計し、製造原価を算出します。これにより、製品ごとの採算性を把握し、コスト削減のための改善点を見つけ出すことが可能になります。また、標準原価と実際原価の差異分析を行うことで、コスト超過の原因を特定し、対策を講じることにも役立ちます。正確な原価管理は、適切な製品価格の設定や、利益最大化のために非常に重要な機能です。
品質管理機能
品質管理機能は、製造される製品の品質を管理するための機能です。製造工程における検査データの記録・管理、不良品の発生状況の追跡、品質問題の原因究明などをサポートします。ロット番号などと連携したトレーサビリティ機能により、特定の製品に問題が見つかった場合に、その製品がいつ、どこで、どの材料を使って製造されたかを追跡することが可能となります。これにより、品質問題の拡大を防ぎ、迅速な対応を行うことができます。製品の品質安定は、顧客からの信頼を得るために不可欠であり、そのための管理を支援する機能です。
生産管理システム導入によるメリット
生産管理システムを導入することで、製造業は様々なメリットを享受できます。生産に関わる業務を一元管理し、情報を「見える化」することで、生産性の向上やコスト削減、業務効率化など、多岐にわたる効果が期待できます。以下では、主なメリットを特徴と共に詳しくご紹介します。
業務の効率化
生産管理システムの導入は、製造業における多岐にわたる業務の効率化に大きく貢献します。これまで手作業や個別のシステムで行っていた生産計画の立案、資材の所要量計算、発注業務、在庫管理、進捗管理といった一連の作業をシステム上で自動化・効率化することが可能になります。これにより、情報の入力や集計にかかる時間を大幅に削減し、担当者の負担を軽減できます。特に、情報がリアルタイムに更新・共有されるため、部署間の連携がスムーズになり、確認作業や手待ち時間の削減にもつながります。結果として、生産プロセス全体のリードタイム短縮にも寄与し、より迅速な製品供給体制を構築できるようになります。
コストの削減
生産管理システムを導入することで、様々な側面からコスト削減を実現できます。例えば、適切な在庫管理機能により、過剰な在庫を削減し、保管コストや廃棄ロスを低減することが可能です。また、正確な所要量計算に基づいた購買管理機能により、必要な資材を必要なタイミングで適切な量だけ発注できるようになり、無駄な仕入れや運送コストを抑えることができます。さらに、生産計画の最適化や工程管理による製造ラインの効率化は、製造にかかる労務費や設備稼働コストの削減にもつながります。これらのコスト削減効果は、製品の原価低減に直結し、企業の利益率向上に大きく貢献します。
納期の短縮
生産管理システムの導入は、製品の納期短縮に有効です。システムによる生産計画の最適化や、製造・工程管理機能による進捗状況のリアルタイムな把握が可能になることで、生産プロセス全体が見える化されます。これにより、遅延が発生している工程やボトルネックを早期に発見し、迅速な対策を講じることができます。また、資材管理機能と連携することで、必要な部品や材料の在庫状況や入荷予定を正確に把握し、手配の遅れによる生産停止を防ぐことができます。これらの要素が組み合わさることで、生産リードタイムを短縮し、顧客からの短納期要求にも柔軟に対応できるようになります。
情報の可視化と共有
生産管理システムの大きなメリットの一つは、生産に関わる様々な情報がシステム上で一元管理され、容易に可視化・共有できるようになる点です。生産計画、受注状況、在庫数、製造進捗、品質情報、原価データなど、これまで各部署で個別に管理されていた情報が統合されます。これにより、担当者は必要な情報にいつでもアクセスできるようになり、迅速かつ正確な状況判断が可能となります。情報のリアルタイムな共有は、部署間の連携を強化し、認識のズレや誤解によるトラブルを防ぐ効果も期待できます。また、製品のロット情報と紐づいたトレーサビリティ機能により、製品の製造履歴や使用部品などを追跡することも可能となり、品質管理やリコール発生時の対応にも役立ちます。
属人化の解消
製造現場における長年の課題の一つに、特定の担当者しか業務内容を把握していない、いわゆる「属人化」があります。属人化が進むと、その担当者が不在の場合に業務が滞ったり、トラブル発生時の対応が遅れたりするリスクが高まります。生産管理システムを導入し、業務プロセスや手順、関連する情報をシステムに集約・標準化することで、属人化の解消につながります。誰でもシステムを確認すれば業務の流れや必要な情報を把握できるようになり、担当者の異動や退職があってもスムーズな引き継ぎが可能となります。また、システムの操作を通じて業務の標準化が進み、全体の生産性向上にも貢献します。
生産管理システムの種類
生産管理システムは、様々な切り口で分類できます。提供される形態や、対応している生産方式によってシステムの種類が異なります。自社の状況やニーズに合ったシステムを選ぶためには、これらの種類を理解することが重要です。
提供形態による分類(クラウド型・オンプレミス型)
生産管理システムは、提供形態によって主にクラウド型とオンプレミス型に分けられます。クラウド型は、インターネット経由でシステムを利用する形態で、自社でサーバーなどのハードウェアを用意する必要がなく、比較的短期間・低コストで導入できるという特徴があります。システムのメンテナンスやアップデートは提供ベンダーが行うため、運用負担が少ないというメリットもあります。一方、オンプレミス型は、自社内にサーバーを設置し、システムを構築・運用する形態です。自社の業務内容に合わせて柔軟なカスタマイズが可能であり、セキュリティ面での安心感が高いというメリットがありますが、初期費用や運用コストが高くなる傾向があります。
生産方式による分類
生産管理システムは、対応している生産方式によっても分類されます。主な生産方式には、見込生産、受注生産、個別生産、ロット生産、繰り返し生産、組立生産などがあります。システムによって得意とする生産方式が異なり、例えば、多品種少量生産を行う企業には個別生産やロット生産に対応したシステムが適しています。繰り返し同じ製品を大量生産する場合は、見込生産や繰り返し生産に特化したシステムが効率的です。複数の生産方式が混在する企業向けに、複数の方式に対応できるハイブリッド型のシステムも提供されています。自社の主要な生産方式や、将来的に導入したい生産方式に合わせてシステムを選定することが重要です。
生産管理システム選定のポイント
生産管理システムの導入を成功させるためには、自社に最適なシステムを慎重に選定する必要があります。市場には様々な種類のシステムがあり、それぞれ特徴や機能が異なります。ここでは、システム選定において重要なポイントをいくつかご紹介します。自社の目的や状況を考慮し、最適な選び方をしましょう。
導入の目的を明確にする
生産管理システムを選定する上で最も重要なのは、システム導入によって何を達成したいのか、その目的を明確にすることです。例えば、生産リードタイムの短縮、在庫コストの削減、品質向上、情報共有の強化、属人化の解消など、自社が抱える具体的な課題を洗い出し、どのような状態を目指したいのかを明確にします。導入目的が曖昧なままシステムを選んでしまうと、必要な機能が不足していたり、オーバースペックなシステムを選んでしまったりする可能性があります。明確な目的設定は、後続のステップである必要な機能の洗い出しやシステム比較の基準となります。
必要な機能を確認する
導入目的が明確になったら、その目的を達成するために必要な機能を具体的に確認します。生産管理システムには、生産計画、在庫管理、工程管理、原価管理、品質管理など、多岐にわたる機能がありますが、すべての機能が必要とは限りません。自社の業務プロセスに照らし合わせ、どの機能が必要不可欠なのか、どの機能があればより業務効率が向上するのかを検討します。将来的な事業拡大や変化にも対応できるよう、システムの機能拡張性も確認しておくと良いでしょう。システムのデモンストレーションなどを通じて、実際に必要な機能が備わっているか、使いやすいかなどを評価することが重要です。
自社の規模や業種に合っているか
生産管理システムは、企業の規模や業種によって最適なシステムが異なります。大企業向けの多機能で大規模なシステムから、中小企業向けのシンプルな機能で導入しやすい小規模システムまで様々です。また、同じ製造業でも、組立製造業、プロセス製造業、個別受注生産、繰り返し生産など、業種や生産方式によって必要な機能やシステム構成が異なります。自社の従業員数、事業規模、そしてどのような製品をどのような方法で生産しているのかを考慮し、自社の実情に合ったシステムを選ぶことが重要です。自社の規模や業種に特化したシステムを選ぶことで、より効率的な運用や高い導入効果が期待できます。
既存システムとの連携
すでに販売管理システムや会計システムなど、他のシステムを導入している場合は、生産管理システムとの連携が可能かどうかも重要な選定ポイントです。システム間で情報をスムーズに連携できることで、データの二重入力の手間を省き、業務効率を向上させることができます。また、各システムのデータを統合的に分析することで、より高度な経営判断が可能になります。システム連携の方式や実績について、事前にベンダーに確認しておくことが重要です。
サポート体制
生産管理システムは、導入して終わりではなく、その後の運用が重要です。システム導入時の設定支援や、運用開始後のトラブル対応、操作方法に関する問い合わせなど、ベンダーのサポート体制が充実しているかを確認しましょう。特に、システムに関する専門知識を持つ担当者が社内にいない場合や、システムの運用に不安がある場合は、手厚いサポートが受けられるベンダーを選ぶことが安心につながります。導入実績やサポートに関する評判なども参考にすると良いでしょう。
まとめ
生産管理システムは、製造業における生産活動を効率化し、QCD(品質・コスト・納期)の最適化を実現するための強力なツールです。生産計画から資材調達、製造、在庫、品質、原価に至るまで、生産に関わるあらゆる情報を一元管理することで、業務効率化、コスト削減、納期短縮、情報共有の促進、属人化の解消といった多くのメリットが得られます。システム選定にあたっては、まず自社の導入目的を明確にし、必要な機能を洗い出すことが重要です。その上で、自社の規模や業種、生産方式に合ったシステムであるか、既存システムとの連携は可能か、そして十分なサポート体制が整っているかといった点を比較検討し、最適なシステムを選ぶことが、導入成功のカギとなります。